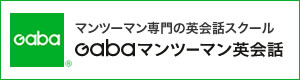裏方のつぶやき「スタッフルーム」
2016.11.8
太古の夢は、葦舟に乗って
こんにちは!Gaba Style Web担当、旅好きのトモです!
みなさんは「葦舟(あしぶね)」と聞いて、何を思い浮かべますか?足(あし)で漕ぐスワンボートを思い浮かべた方もいるかも知れませんね。「葦(あし)」とは湿地帯などに生息する植物で、簾(すだれ)や葭簀(よしず)の材料となる細長い草、葦舟はその葦で造られた舟です。

前回のスタッフルームで、私が若い頃に南米ペルーに住んでいたお話をさせて頂きましたが、ペルーのアンデス山脈に跨るチチカカ湖には、葦でできた浮き島に住み、葦でできた家に住み、葦でできた舟で漁をする人々がいます。葦でできた島に上陸すると、足元がふわふわします。一説によると、インカ帝国の攻撃から逃れようとした人々がチチカカ湖に葦を投げ込み島を作ったとか。彼らにとって、葦は切っても切れないものなのです。日本でも、葦船は古事記に登場するほど古い歴史を持っています。

そんな葦の舟に魅了された冒険家がいます。彼の名前は石川 仁(いしかわ じん)。私がペルーにいた頃、何人かの日本人が私と同じように日本人向けのツアーガイドをしながら、インカ帝国の首都と言われるペルーの「クスコ」と言う町に長期滞在しいました。彼もそんなガイド仲間の一人でした。仁ちゃん(と、いつもと同じ呼び方でこの文中では書かせて頂きますね!)は私がペルーで出会う前から、サハラ砂漠をラクダで横断したり、アラスカでイヌイットと暮らしたり、ジャングルを川下りしたりと面白い旅をしていて、その冒険談を同じ宿にいた私達にもよく聞かせてくれたものでした。
彼はペルー滞在中の当時、仲間4人と共に葦船で標高3800mにあるチチカカ湖を4か月かけて一周すると言う冒険を成し遂げ、それが縁となって、その後も日本での葦船の第一人者として活躍しています。仁ちゃん曰く、葦の様な植物は世界中至るところに自生していて、大昔の技術でも十分に舟を造ることができたそうです。そして、GPSもなかった時代にも、星を読んで海を渡る人々がきっといたはずだと。

現在 仁ちゃんは太古の人々が葦舟で黒潮に乗って広い海を渡り、大陸から大陸へ文化を伝えた事を実証すべく、2年後にアメリカから日本まで太平洋を横断するプロジェクトを進めています。その傍ら、日本全国で葦船学校(ワークショップ)を開いて、葦舟を造り、そして乗るという体験を広める活動をしています。私も先日 伊豆で行われたワークショップへ参加してきたので、その時の様子を少しご紹介させて頂きますね!

ワークショップは二日間に渡り、一日目は舟の本体と波除けを造り、二日目はそれを合体させて舟の形に成形し、乗船!という流れでした。小さな葦舟づくりは工程としてはとてもシンプルで、草を刈り、束ね、叩いて引き締め、舟の形に成形する、それだけです。こうして書くと簡単そうですが、すべて人力で行うため、時間も労力もとてもかかります。刈られた葦をロープで束ね、「せーのっ!」の掛け声とともに参加者全員で代わる代わるロープを力いっぱい引っ張っては木槌で思い切り草の束を叩き、こうした作業の積み重ねのうちに、それがだんだん舟らしくなって行くのは、まるで魔法を見ている様でした。

舟が完成すると、川に浮かべる前に進水式と言う儀式を行います。お神酒と南米式の大地の神パチャママに捧げる祝詞を上げて船出の安全を祈った後、いよいよ舟を川まで運び乗船です!参加者は子供たちから順番に次々に舟に乗り、歓喜の声を上げました。

ごく普通の、ただの草の束から舟ができること、自分で造った舟に乗れることは、実際にやってみると大きな感動がありました。そして役目を終えた日には、草の舟はバラバラになって自然の中へと消えて行きます。そう、葦舟は究極のエコな乗り物なのでした。
この記事を読んで葦舟や仁ちゃんの冒険談に興味を持った方は下記リンクをチェックしてみてください。仁ちゃんは今、日本全国でトークライブも行っています。あなたの冒険心に火をつけちゃうかも知れません!

◆探検家 草船航海士 石川仁(イシカワ ジン)
オフィシャルサイト
http://jinishikawa.com
◆カムナ葦船プロジェクト~太古の智慧をつなぐ旅~
http://kamuna.net
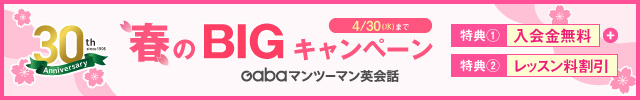

 【Gabaからのお知らせ】
【Gabaからのお知らせ】 【特集】
【特集】 【英単語の正しい使い分け】
【英単語の正しい使い分け】 【使いこなす句動詞】
【使いこなす句動詞】